NEWS
中小企業のAI社内ルール(2026年度版)|安全な利用・懲戒・情報管理の実務ガイド
2025/11/10
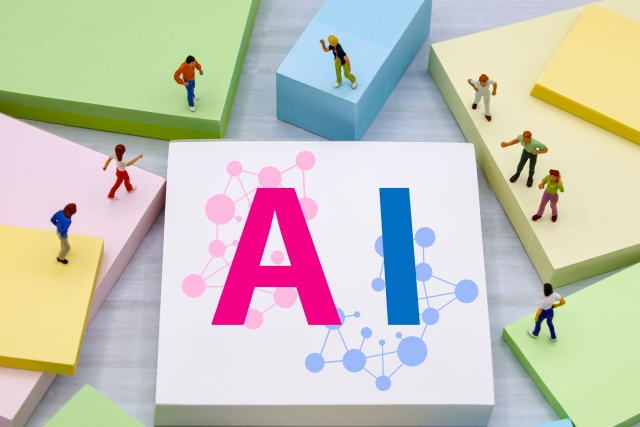
監修:RESUS社会保険労務士事務所 山田雅人(労務・情報管理アドバイザー/AI活用コンサルタント)
1. はじめに|AI活用は“企業活動から切り離せない時代”に
インターネットの普及、スマートフォンの一般化と同じように、生成AIは「使う企業」と「使わない企業」で圧倒的な差が生まれる技術です。
しかしその一方で、中小企業の経営者からは次のような不安の声も多く聞かれます。
-
従業員が勝手にAIを使っても大丈夫なのか?
-
会社でAI費用を負担してよいのか?
-
個人情報や顧客情報は漏れないか?
-
誤情報を使った場合の責任は誰が負うのか?
-
ルールを逸脱したら懲戒できるのか?
これらは、どれも自然な疑問です。
実際に、AIは便利である反面、情報漏えい・誤情報利用・著作権問題・契約違反など、従業員が“悪意なく”引き起こすリスクが潜んでいます。
だからこそ今、中小企業には「AIを安全に使うための社内ルール(ガイドライン)」の整備が必須になっています。
本ページでは、中小企業でも即導入できるよう、安全性・労務・情報管理・法務のすべてを網羅した実務ガイドを公開します。
2. AI活用の主なリスク(企業がまず把握すべき4領域)
2-1. 情報漏えいリスク
-
入力した情報が外部に送信される仕組み
-
無料AIでは「情報学習」の可能性
-
商用版AIでは「学習禁止設定(非学習モード)」が利用可能
2-2. 誤情報(ハルシネーション)
生成AIは“もっともらしくみえる誤情報”を出すことがあります。
例:
-
最新法令を誤って伝える
-
不正確な契約条文を作成する
-
医療・介護・安全衛生に関する情報の誤記載
→ 誤情報利用による事故は企業責任となり得ます。※AIが間違えた場合でも、企業側が「誤った情報を使った責任」を問われる点が重要です。
2-3. 著作権・法務リスク
-
他社記事の「丸写し」になる文章が生成される場合がある
-
特許・商標に触れる案が出ることもある
-
契約書の自動作成で誤条文が混入するリスク
2-4. 労務管理・コンプライアンスリスク
-
従業員の私用アカウント利用
-
無断で顧客情報をAIに入力
-
AI依存による判断ミス
-
権限なき者の契約書作成
-
秘密保持義務違反
3. 企業がまず決めるべき「AI入力禁止情報」
AI活用ルールで最重要となる部分です。
【NG(絶対禁止)】
✅ 個人情報(氏名・住所・電話番号・メールなど)
✅ 顧客情報・クレーム内容・問い合わせ内容
✅ 契約書の全文(相手方固有の内容)
✅ 売上データ・給与データ・財務情報
✅ 社内機密(価格戦略・仕入先情報・技術情報)
✅ 社員の評価情報・人事情報
【条件付きでOK】
✅ 匿名化されたデータ(Aさん→「従業員1名」)
✅ 数字・金額を丸めたデータ
✅「例示」に変換した架空シナリオ
✅ 業務フローやマニュアルの形式指定
【安全に入力するためのポイント】
-
固有名詞はすべて伏せる
-
生データは入力しない
-
実案件をそのまま入力しない
-
図面・画像・契約書PDFは基本NG(高リスク)
4. AI利用を許可する範囲を明確にする
会社としては、以下の点を必ず決めておく必要があります。
✅「業務でAI利用を許可するか?」
→ 許可する場合、会社が認めるAIツールを指定
(例:ChatGPTチーム版、Microsoft Copilot など)
✅「AI利用の費用は会社負担でよいか?」
→ 業務利用が前提なら会社負担が原則(福利厚生ではない)
✅ 私用アカウントの利用は禁止
→ 無料版や個人アカウントは「情報学習」の可能性が高く危険。
✅ 会社支給アカウントを付与する
→ 権限管理・ログ管理が必須。
5. AI利用ガイドラインの“必須項目”
以下を明文化すると、トラブルの9割を防げます。
5-1. 利用目的
-
業務効率化、ミス削減、文書品質向上
-
必ず「業務の範囲内で使用すること」
5-2. AI入力禁止情報
(先述の絶対NGリスト)
5-3. AIで作成してよい文書・NGの文書
✅ 初稿・草案(案内文、マニュアル、提案書)
✅ Excel関数・計算式
✅ 点検・校正(誤字脱字、論理不整合)
❌ 重要契約書の全文
❌ 社内の意思決定文書
❌ 労務・法務・税務の最終判断
❌ 社員評価・懲戒書類
5-4. 最終判断は「人間」が行う
-
AI回答は“あくまで案”
-
専門分野は専門家の点検が必須
5-5. バージョン管理・ログ管理
-
AIが編集した文書にはバージョンを付ける
-
部署ごとに履歴を残すルール
5-6. トラブル報告ルート
-
利用ミスが疑われる場合は担当者へ即時連絡
-
情報漏えいは上長→経営者へ報告の三段階
6. ガイドライン逸脱時の「懲戒」について
法律的には、AI利用ルールを逸脱した場合でも就業規則に規定があれば懲戒は可能です。
✅ 懲戒可能なケース
-
個人情報・顧客情報を無断入力
-
私用AIを使い機密情報を漏えい
-
虚偽情報を使って業務上の損失や迷惑を発生させた
-
ルール違反を繰り返す
✅ 懲戒のために必要な要件
-
就業規則に「AI利用ルール違反」に関する根拠がある
-
具体的な社内ルール(ガイドライン)が明文化されている
-
社員に周知している(説明・配布・研修・教育)
-
過程・証拠・損害が明確である
→ 適正な手続を欠く懲戒は無効となるおそれがあるため、ルール整備が前提。
✅ 懲戒ではなく「指導・注意」で十分なケース
-
無意識の操作ミス
-
教育不足によって発生した誤利用
-
軽微な判断ミス
※初期は“教育・指導重視”で運用する企業が多い。
※本ページは一般的な情報提供であり、特定の事案に対する法的助言ではありません。運用前に就業規則・労使協定・個人情報保護規程との整合をご確認ください。必要に応じて、顧問社労士・顧問弁護士とも調整のうえ導入ください。
7. AI活用に必要な「社内研修」
ルールを作るだけでは不十分で、最低限の教育が必要。
教育内容(中小企業向け)
✅ 安全な入力方法
✅ 入力禁止情報
✅ AIの誤情報の見抜き方
✅ プロンプト(指示文)の基本
✅ 文書校正方法
✅ バージョン管理のルール
研修は年1回が推奨
AI仕様・法令が毎年変わるため、定期更新が必須。
8. AIガイドライン(社内規程)ひな形
※御社カスタマイズ版は別途作成可能です。
【AI利用ガイドライン(抜粋例)】
1. 目的:業務効率化・品質向上を目的として生成AIを安全に利用する。
2. 適用範囲:役員・社員・契約社員・パート・委託先(必要に応じ別紙)に適用。
3. 利用ツール:会社が指定した商用AIに限る。私用アカウントの業務利用を禁ずる。
4. 入力禁止情報:個人情報、顧客情報、機密情報、取引先固有情報、契約書全文等。
5. 生成物の位置付け:AI生成物は初稿とし、最終判断は人が行う。専門分野は専門家の点検を要する。
6. データ管理:版管理・ログ管理を行い、編集履歴を保全する。
7. 事故対応:漏えい・誤情報使用等を認知した場合は直ちに上長→情報管理責任者→経営者の順に報告する。
8. 禁止事項:本ガイドライン違反、権限なき外部提供、私用アカウント利用等。
9. 罰則:就業規則に基づき、故意・重過失等に限り懲戒の対象となることがある。
10. 教育:年1回以上の社内研修を実施し、本ガイドラインの周知と更新を行う。
→ 上記のような内容で社内規程にしておくことで、ルール違反時にも法的に整合性のある運用ができます。
9. まとめ|AIは「便利」ではなく“必須インフラ”になる
インターネットがなかった時代に戻れないように、スマートフォンなしで仕事ができないように、AI活用は企業活動の前提条件になります。
中小企業こそ、AI活用で次のような変化が現実的になります。
-
作業時間の大幅短縮
-
ミスや属人化の解消
-
顧客対応のスピード向上
-
社員のストレス軽減
-
新サービス開発
-
経営の意思決定が早くなる
そして何より、“安全に使えるルール”が整っている企業だけが、AIを武器に変えられます。
10. AIガイドライン作成をサポートします
次のような支援を提供しています:
✅ AI導入の初期相談
✅ AI利用ルール(ガイドライン)作成
✅ 就業規則への懲戒規定反映
✅ 情報管理ルールの策定
✅ 文書作成・点検のAI化
✅ 業務棚卸し(AI適用診断)
✅ 社内AI研修の実施
\初回相談無料・お見積もり無料/
▶ 今すぐお問い合わせ(フォーム)
関連ページ
▶中小企業のためのAI導入チェックリスト30項目 ― 導入前・導入後に絶対押さえるべきポイントを専門家が体系化 ―
▶中小企業のためのAI活用ガイド ― 業務効率化・売上向上・人材不足解消を実現する実務レベルのAI活用法 ―
▶中小企業向け 社内AI研修サービス|情報漏えい防止・業務効率化を実現する実務研修
▶中小企業のAI事故対応ガイド|情報漏えい・誤情報・顧客トラブルの初動と再発防止を専門家が解説