NEWS
【2026年対応版】メンタルヘルス不調と企業対応|ストレスチェック・休職・復職支援の実務ポイント(社労士監修)
2025/10/07
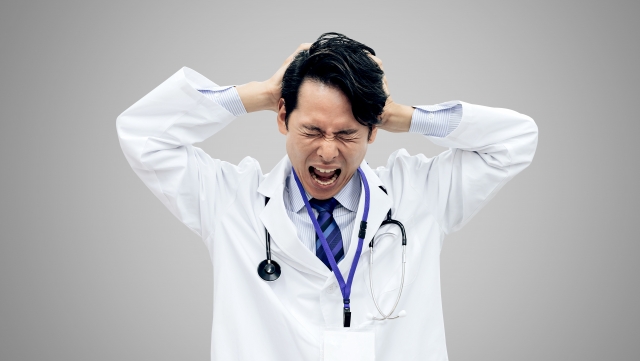
はじめに|メンタル不調対応は“労務管理の最重要テーマ”
うつ病・適応障害・不安障害などのメンタルヘルス不調は、今や特定業種に限らずあらゆる企業で増加しています。
厚生労働省の統計では、労災請求のうち「精神障害」が占める割合が年々増加しており、人材流出・労災認定・損害賠償請求につながる重大リスクとなっています。
特に中小企業では、
-
休職規程が整備されていない
-
復職判定の基準が曖昧
-
ハラスメント要因への対応不足
といった理由から、労務トラブルに直結する事例が少なくありません。ある日突然「体調不良のため休業したい」と医師の診断書を提出されることは、人事担当者にとって大きな不安材料です。
本記事では、企業が押さえておくべき「ストレスチェック」「休職制度」「復職支援」「判例リスク」を体系的に整理し、社労士の視点から解説します。
第1章|企業が負う法的義務と社会的責任
労働安全衛生法とストレスチェック制度
-
従業員50名以上の事業場は年1回の実施義務
-
実施体制(実施者:産業医や保健師)を明確にする必要
-
結果は従業員本人へ通知、組織単位での集団分析も可能
-
高ストレス者への医師面接指導を実施する仕組みが求められる
労働契約法第5条「職場環境配慮義務」
労働契約法第5条では「使用者は労働契約に伴い労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務」を規定。
これは『心身の健康(メンタル含む)』にも及ぶとされ、違反すれば損害賠償責任が発生し得ます。
社会的リスク
-
ハラスメント事案とメンタル不調が重なると、企業のブランド毀損に直結
-
SNS炎上、離職ドミノ、採用難へと波及
→関連ページ:【2025年対応版】ハラスメント発生時の初動対応と改善計画
第2章|ストレスチェックの活用と実務上の工夫
単なる形式実施では不十分
法律上は義務を果たしていても、「やって終わり」ではリスクは減りません。
有効活用のポイント
-
集団分析で組織課題を把握
部署別に「長時間労働」「人間関係要因」が見える化される -
改善施策の具体化
-
就業規則の見直し(労働時間管理・休職規程)
-
ハラスメント研修との連動
-
管理職へのマネジメント研修
-
→関連ページ:【2025年対応版】職場のイライラ解消と雰囲気改善研修
第3章|休職制度の設計とトラブル防止
就業規則に盛り込むべき要素
-
休職開始要件(医師診断書・勤務困難の判断基準)
-
休職期間(例:最長6か月/12か月など)
-
休職中の処遇(社会保険料、賞与、昇給の取扱い)
-
復職判定手続(主治医意見書+産業医面談+会社判断)
-
休職満了時の取扱い(自然退職規定の有無)
実際によくあるトラブル
-
診断書=無条件休職と誤解
-
復職基準が不透明で従業員と争いになる
-
休職期間満了後の解雇・退職手続が曖昧で紛争化
→関連ページ:【2025年対応版】就業規則作成サービス徹底比較
第4章|復職支援とリワーク制度
復職判定のフロー
-
主治医の「就労可」意見書
-
産業医面談・人事ヒアリング
-
試し出勤(リワーク勤務)で段階的調整
-
本復職可否の最終決定
再発防止の具体策
-
業務量を段階的に増加させる
-
勤務時間を短縮から通常へ
-
上司・同僚との定期面談を実施
-
ハラスメント要因の改善、組織風土改革
→関連ページ:【2025年対応版】絶妙なモラハラ事例集
第5章|判例・行政対応に学ぶリスク
-
長時間労働+上司の叱責→うつ病発症→労災認定
-
復職拒否判断の不透明さ→解雇権濫用で無効判決
-
復職支援を怠ったことで数百万円~数千万円の賠償命令
判例に共通するのは、「規程が不十分」「記録が曖昧」という点。
制度整備と運用記録がリスク回避のカギです。
第6章|RESUS社労士事務所の支援サービス
-
ハラスメント防止研修・社内アンケートとの組み合わせによる総合的支援
→関連ページ:【2025年対応版】社内アンケート・ES調査代行サービス
FAQ|よくある質問
Q1. 休職規程は就業規則に必ず必要ですか?
A. 義務ではありませんが、メンタル不調者が出た際に規程がないと「裁量対応」になりトラブルが多発します。必ず設けることを推奨します。
Q2. 診断書があれば必ず休職させなければなりませんか?
A. いいえ。診断書は判断材料の一つにすぎません。就業規則や会社の判断基準を踏まえ、産業医面談と合わせて判断します。
Q3. 復職判定は医師の意見だけで決めるのですか?
A. 主治医の意見は重要ですが、最終判断は会社にあります。職場での勤務継続可能性を考慮する必要があります。
Q4. 中小企業でもストレスチェックは必須ですか?
A. 従業員50名未満は努力義務ですが、メンタル不調防止・補助金申請の観点から実施を推奨します。
Q5. 社労士に相談するメリットは?
A. 制度設計・就業規則整備・判例知識に基づく実務対応までトータルでサポートできる点です。医師や弁護士と異なり、労務管理と実務運用を橋渡しできるのが強みです。
Q6. 休職中の社会保険料はどうなりますか?
A. 在籍している限りは原則として会社・本人ともに負担が続きます。賃金が出ない場合は、従業員に立替払いを依頼するか、給与精算時にまとめて控除する方法が一般的です。
まとめ|メンタル不調対策は“攻めの人事戦略”
-
メンタルヘルス不調は「誰にでも起こり得る」現実的な労務リスク
-
制度整備・記録・教育の3点セットで予防が可能
-
ストレスチェック→休職制度→復職支援の流れを整えることが企業防衛の要
2025年は「ハラスメント防止」「働き方改革」に加えて、メンタル不調対応が人事戦略の中心に据えられます。
お問い合わせはこちらから
貴社の現状に即した制度設計や運用アドバイスをご希望の方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。
\初回相談無料・最短翌日対応/
\就業規則・休職復職支援のご相談実績200社以上/