NEWS
【2026年版】職場の迷惑行為対応マニュアル|パワハラとまでは言えない“不機嫌態度・行動”をどう注意すべきか(社労士監修)
2025/10/29
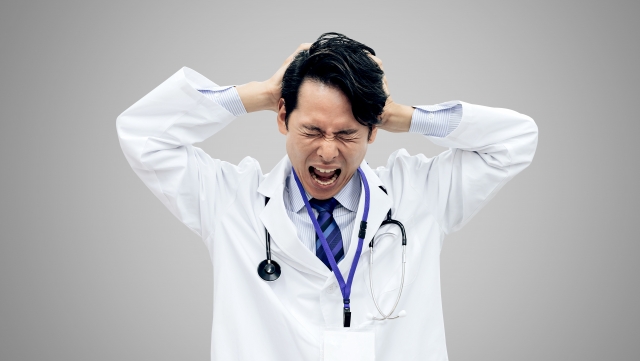
― パワハラでもカスハラでもモラハラでもない、“嫌な行為”への実務対応 ―
(監修:RESUS社会保険労務士事務所/社会保険労務士 山田雅人)
はじめに|「ハラスメントではないけれど嫌な行為」が増えている
職場では、パワハラやモラハラ、カスハラとまでは言えないが、何となく嫌な行為。放置すると職場が冷え切るような“迷惑行為”が少なくありません。
例えば――
-
溜息を何度もつく、あくびを繰り返す
-
軽い舌打ちや無言での圧力(不機嫌そうな顔)
-
目をほとんど合わせない、返事も「ふん、ほー、へー」だけでほとんどしない
-
スマホに夢中で気のない対応。無関心で話を聞いているように見えない
-
挨拶をしない、必要最低限しか話さない、話しかけない。
これらは違法性がなくても、チームの士気や信頼関係を壊す行動です。
にもかかわらず、企業としては「パワハラでもないから処分しづらい」「注意したら反発されるのでは」と対応をためらいがちです。
しかし、このような行為を放置すると、職場全体が冷え切り、モチベーション低下や離職、事故の見落としにまでつながります。
第1章 放置された“迷惑行為”が職場に与えるリスク
1.1 ハラスメント未満でも組織不全を起こす
小さな態度の乱れや無言の圧力は、放置されると職場の空気を変えます。
特に小規模事業所では、関係性が近いがゆえに緊張感が高まり、誰も注意できない沈黙の職場が形成されることも。
たとえば、
製造業の5人チームで、1人が常に不機嫌・無言対応。
注意を避け続けた結果、他メンバーが報告を控えるようになり、結果的に軽微なミスが発見されず機械事故に発展――。
行為者の態度そのものが直接的な損害を与えなくても、チーム内の心理的安全性を崩す間接的リスクを生じさせます。
第2章 なぜ注意・指導が難しいのか
2.1 “すり替え型反発”への注意
迷惑行為を注意すると、本人が逆に会社の待遇・運営・人事制度の問題を指摘し、「自分は被害者だ」「原因は会社にある」と論点をすり替えるケースがあります。
→ こうした場合は、感情的に議論せず、「行動」「影響」「職務上の支障」という事実ベースの話に戻すことが重要です。
例:
✖「不満があるのはわかるけど、態度を直して」
○「あなたの態度が原因で報告が止まっており、業務に支障が出ています」
2.2 “無自覚・無反省”への注意
嫌な態度を注意すると、「こういう性格」「誰にも迷惑をかけていない」「人格否定ではないか」と開き直り、反省しようとしないこともあります。
→ こうした場合も、感情的に指摘せず、まずは「不機嫌そうな態度に見えるため、他のスタッフが委縮している」事実を伝えることが必要です。
例:
✖「性格を直した方がよいよ」
○「不機嫌と誤解されることもあるから、挨拶くらいは元気よくしてみよう」
第3章 指導的立場の担当者が取るべき注意・指導の進め方
3.1 まずは“話を聴く”姿勢を示す
小規模な職場では、いきなり注意するよりも、「◎◎って言ってたみたいだけど、どうしたの?」と声をかける方が効果的です。
実はこの“聴取”自体も面談記録と扱うことができ、本人の誤った主張や逆に問題となった背景を把握する重要な材料になります。
→ こうした『対話型の記録』は、のちに問題が発展し、懲戒や評価判断が必要になった際には、「十分な聴取と改善機会を与えた」ことを強化する証拠にもなります。
3.2 指導記録を残す
一度注意しただけで賞与や昇給に影響を与えるのは時期尚早です。
しかし、継続的な態度変化の有無を記録しておくことで、「改善努力を求めたにもかかわらず変化がない」という客観的根拠ができます。
記録のポイント:
-
注意日・行為内容・影響・本人の反応
-
対話・支援・フォロー内容
-
指導後(面談後)の行動変化
※ 形式はメモ・メール・面談記録・報告書など。フォーマットよりも“継続性”が重要です。
3.3 懲戒まで進むためのステップ
-
単発的・軽度な行為では処分は難しい
-
「繰り返し」「改善意欲の欠如」「他者への悪影響(職場環境を害する)」があれば懲戒判断の材料に
-
書面注意 → 指導記録 → 就業規則違反の整理 → 懲戒処分 という順で段階的に対応
✅ 実務上の考え方
懲戒は「制裁」ではなく「秩序維持のための必要最小限の措置」。少人数で現場を回す中小企業の目的はあくまで改善であり、大企業のように処分することをゴールとしてはいけません。なお、懲戒処分に進む際は、就業規則に基づく手続きと本人への弁明機会の付与が不可欠です。
第4章 “聴く・伝える・支える”を軸にした対応
職場の人間関係は、簡単に「叱る・叱られる」よりも、粘り強く「聴く・伝える・支える」の循環によって改善します。
| 段階 | 行動 | 目的 |
|---|---|---|
| Step1 | 聴く(背景を知る) | 行為の理由・本人の不満・ストレス要因を把握 |
| Step2 | 伝える(行動と影響を共有) | 感情ではなく事実ベースで注意する |
| Step3 | 支える(改善機会を与える) | 行動目標やサポートを提示し、再発防止へ |
第5章 職場の文化として“嫌な行為を放置しない”を定着させる
-
行動指針やクレドに「人を尊重する行動」を明文化
-
会議・朝礼などで“態度も仕事の一部”と伝える
-
小さな注意をしやすくする“報告しやすい空気づくり”
-
管理職研修で「行動フィードバック」の手法を学ぶ
-
匿名相談・外部相談窓口の併用で公平性を担保
第6章 判例・行政指導のヒント
| 事例 | 概要 | 示唆 |
|---|---|---|
| 東京地裁H30.2.8 | 管理職が一時的に声を荒げたが継続性なし | 一過性の指導はパワハラに該当しないが、再発防止の指導必要 |
| 札幌地裁R2.5 | 無視・排除的態度が続き、上司が放置 | 使用者の職場環境配慮義務違反を認定 |
| 厚労省指針 | 同僚間の嫌がらせ・無視も対象外とは限らない | 職場秩序や心理的安全性を害する場合は注意・是正対象 |
第7章 明日からできる第一歩
-
「挨拶・返事・感謝」を組織のルールにする
-
行動記録を“事実メモ”として残す
-
小さな違和感はその日のうちに話す
-
面談で“本人の背景”を聞く(不満・ストレス・疲労)
-
注意の目的を「関係修復」と位置づける
FAQ|人事担当者がよく悩むポイント
Q1. 態度が悪いだけで注意していいの?
→ 業務への影響があれば可能です。「報連相が滞る」「若手社員が萎縮している」「気を使いすぎて心理的安全性が低い」など、具体的な支障を記録しましょう。
Q2. 一度注意しても改善しない場合は?
→ 同じ内容が続く場合、次回は「指導履歴」を基に書面で指摘。その際は“改善目標”を明確に提示します。
Q3. 小規模事業所で注意しにくいときは?
→ 同僚や上司がまず「どうしたの?」と声かけを。それ自体が“聴取記録”となり、のちの評価・処分対応の裏付けになります。
Q4. 指導後に本人が「会社のせい」と反論してきたら?
→ 感情的に応じず、「話題を行動に戻す」のが原則。会社の制度改善は別途議題とし、混同させないことが重要です。
まとめ
-
軽度な迷惑行為でも、放置は“組織の冷え”を招く。
-
指導は感情でなく事実ベース。
-
記録・聴取・支援を積み重ねることで、公正な判断につながる。
-
“叱る”より“聴く”が、職場の信頼を取り戻す第一歩。
参考リンク
▶なぜ管理職者教育は失敗するの?|人事労務と心理学から考える“現場育成の限界”
▶職場のイライラ解消と雰囲気改善|ハラスメント防止・コミュニケーション研修のご案内
▶外部ハラスメント相談窓口【月額5,500円】|パワハラ・カスハラ・内部通報に対応【全国対応】