NEWS
【2025年版】通勤手当の見直し相談が急増中|規程作成の実務ポイントを社労士が解説
2022/06/16
(最終更新日:2025/09/30)
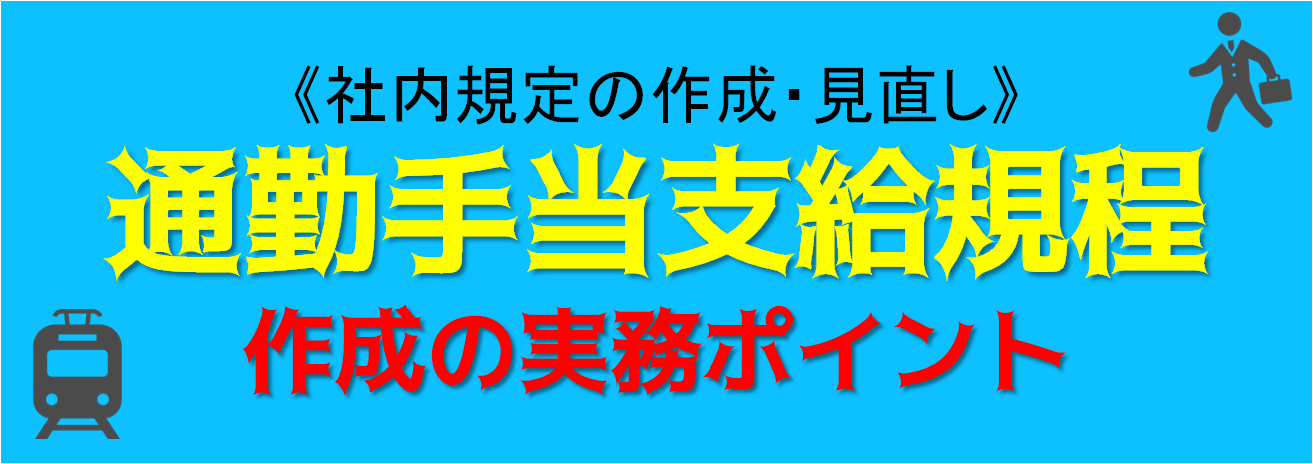
はじめに|通勤手当が“見直し対象”になる理由
新型コロナ禍を契機に導入された在宅勤務・テレワークは一時的な措置にとどまらず、恒常的な勤務形態として定着しました。
その結果、従業員の通勤頻度や通勤手段が大きく変化し、企業からは「通勤手当の支給ルールを見直したい」という相談が急増しています。
これまで「住宅手当」「家族手当」などの主要手当が見直し対象でしたが、今や通勤手当の在り方までもが企業の経営課題となっています。
通勤手当の法的位置付け
まず押さえておくべきは、通勤手当は法律上の支給義務がないという点です。
-
労働基準法や関連法令に通勤手当の支給義務規定はなし
-
あくまで福利厚生の一環として企業が任意に支給できる制度
ただし、従業員にとっては生活費を補う重要な収入源であり、安易な廃止や不利益変更は労働契約法上の「不利益変更」とみなされるリスクがあります。
通勤手当規程に盛り込むべき基本事項
通勤手当を規定する際は、以下の項目を明記する必要があります。
-
支給対象者の範囲と除外対象者
-
対象となる通勤手段と申請方法
-
支給額の計算方法・支給単位
-
マイカー・バイク利用者の取扱い
-
申請方法・申請義務と添付書類
-
紛失・不正利用時の措置
-
退職・転勤時の精算ルール
規程設計の実務ポイント
1. 支給対象者の範囲と除外対象者
-
距離制限を設ける場合は「直線距離」か「最短経路」かを明記
-
アルバイト・パートを一律除外する規定は同一労働同一賃金ルールに抵触する恐れがあるため、労働時間や勤務日数で区分するのが適切
2. 対象となる通勤手段
-
鉄道・バスのみか、自転車・マイカー・バイクも含むかを明記
-
複数交通手段の併用可否や、例外(障害や高齢等による特別承認)の有無も記載
3. 支給額と計算方法
-
定期代(1か月/3か月)または実費精算を採用
-
マイカー利用は燃料費換算式を規定例として活用可能
-
支給額の上限を明示し、精算ルールを合わせて記載
4. マイカー利用のリスク管理
-
運転免許・保険加入の確認
-
飲酒運転・危険運転等の禁止規定を明文化
-
安全運転義務を怠った場合の処分規定を設ける
5. 申請・変更義務
-
入社時・引越時・運賃改定時の申請を義務化
-
不正受給や過払い発覚時の返還規定を明記
6. 紛失・不正利用の措置
-
定期券紛失時の費用負担区分を明記
-
故意・重過失による不正は処分対象とする規定が必須
7. 退職・転勤時の精算
-
長期定期支給時の未使用期間分は返還対象とすることを明文化
-
有給休暇消化中の扱いをルール化しておくことでトラブル回避
最近のトレンドと相談事例
-
テレワーク定着に伴い「通勤回数に応じた日割精算」へ移行
-
自転車通勤者への補助(駐輪場代や保険料補助)を導入
-
通勤手当を縮小し、その分を在宅勤務手当に振替
企業の実情や従業員の働き方に応じ、制度を柔軟に再設計する動きが加速しています。
まとめ|“当たり前”の制度ほどトラブル防止が大切
通勤手当は「任意規定」ではありますが、働き方が多様化する今だからこそ、詳細ルールの整備が必要です。
-
不公平感や不正受給を防止
-
トラブル時の法的リスクを低減
-
従業員の納得感を高めて人材定着につなげる
当事務所のサポート
RESUS社会保険労務士事務所では、
-
通勤手当支給規程の新規設計
を行っています。
原案なしで起案から:8万円/原案ありの見直し:5万円/添削:1ページ1万円 が目安です。
\初回相談無料・お見積り無料/
▶ [お問い合わせフォームはこちら]
関連記事
©RESUS社会保険労務士事務所