NEWS
BYODとは?私用スマホを業務利用する際の労務管理・就業規則・セキュリティ対策【2026年最新版】
2019/08/26
(最終更新日:2025/08/25)
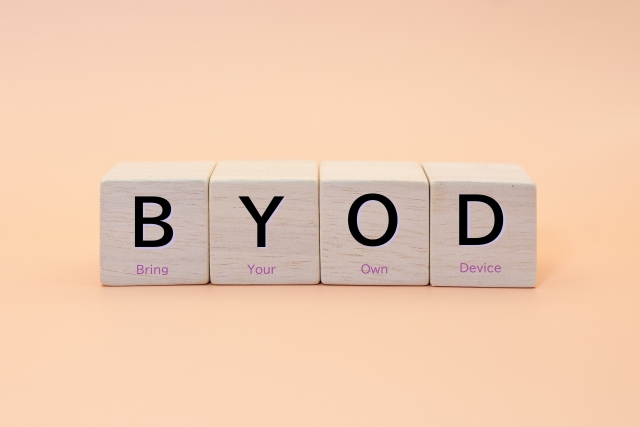
はじめに:なぜ今「BYOD」が課題なのか
スタートアップや中小企業では、私物のスマートフォンやPCを業務利用する「BYOD(Bring Your Own Device)」が一般化しています。
新型コロナ禍以降のテレワーク普及に加え、「常に自分のスマホが手元にある」働き方 は今や当たり前。
一方で、SNSへの不適切投稿や情報漏洩、そして 生成AIアプリに誤って社内データを入力して流出する事故 など、新しいリスクが増大しています。
国内でもBYOD利用者は1,000万人超ともいわれ、「うちは小規模だから大丈夫」では済まされない時代 になっています。
「BYODを許可するかどうか」ではなく、「どのように管理するか」が問われる時代になっています。
BYODのメリットとデメリット
✅ 従業員のメリット
-
使い慣れた端末で効率アップ
-
荷物が減る(仕事用と兼用できる)
-
私用アプリとの一括管理が可能
-
柔軟な働き方を実現
✅ 会社のメリット
-
機器購入・通信費を削減
-
導入教育が不要(既存端末利用)
-
IT管理コストを軽減
-
従業員満足度の向上
⚠️ 従業員のデメリット
-
通信費などの業務利用分も自己負担
-
アプリ利用制限の可能性
-
プライベートと仕事の切り分けが困難
-
プライバシーへの懸念(監視される不安)
⚠️ 会社のデメリット
-
業務データと私用データが混在
-
端末紛失・ウイルス感染による被害拡大
-
退職時にデータ削除が徹底できないリスク
-
情報漏洩時の企業責任
会社が最低限行うべき対策(2025年版)
1. 社内ルール・就業規則の整備
-
BYOD利用規程を作成し、就業規則に明記(労基法第89条・相対的必要記載事項)
-
秘密保持誓約書に署名させる
-
デバイス利用申請書を導入(端末登録制)
※「一切責任を負わない」といった免責条項は無効リスクが高いため、
→ 「故意または重大な過失がある場合に賠償」 とするのが適切です。
2. 技術的対策
-
MDM(モバイルデバイス管理):遠隔でデータ消去やアプリ制御が可能
-
ゼロトラスト認証:個人ごとのアクセス制御を強化
-
二要素認証:パスワード+認証コードでセキュリティ向上
-
暗号化と証明書管理:業務データを端末内に残さない仕組み
▶中小企業ではコスト面からフル導入が難しい場合もありますが、「リスクをゼロに近づける」ために上記は検討する価値があります。
3. 労務管理上の配慮
-
業務連絡が休日や深夜に行われた場合は「労働時間」として算定される可能性が高い
-
未払い残業代請求リスクが大きいため、
→ 管理職への教育(業務指示のタイミング・範囲を制御)必須 -
在宅勤務規程やフレックスタイム制度と連動させて運用するのが望ましい
▶「時間外の業務連絡ルール」を明確化し、管理職研修で意識改革を行う必要があります。
《参考資料》規程ひな型
第1条(目的)
従業員が私有するスマートフォン・PC等を業務に利用する際の取扱いを定める。
第2条(対象者)
正社員・契約社員・パート・アルバイト等すべての従業員に適用する。
第3条(利用申請)
利用希望者は事前に申請を行い、会社の承認を得なければならない。
第4条(機密情報の取扱い)
秘密情報は「社外秘」と明示し、漏洩防止に努める。
第5条(退職時の措置)
退職者は業務データを完全削除し、誓約書を提出する。
第6条(費用負担)
通信費・端末費用は原則従業員が負担する。
第7条(責任)
故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合、従業員は賠償責任を負う。
第8条(調査権限)
合理的理由がある場合、会社は端末調査・アクセス制御を実施できる。
よくある質問(FAQ)
Q1. BYODを禁止すれば安全ですか?
A. 禁止しても「シャドーIT」(無断利用)は発生します。禁止方針であっても、違反時の規定整備は必要です。
Q2. 通信費は会社が負担しないと違法ですか?
A. 違法ではありません。ただし業務に通常必要な通信費は会社が負担するのが望ましい。ただしBYODの性質上、合理的範囲で従業員負担とすることは可能。
Q3. 労働時間の記録はどうすれば?
A. 業務アプリのログやチャット記録が残るため、使用状況をもとに労働時間と認定されやすいです。勤務ルールを事前に定めておきましょう。
Q4. 情報漏洩が発生したら?
A. 個人情報保護法改正により、漏洩時は速やかに個人情報保護委員会へ報告義務があります。規程に緊急対応フローを組み込む必要があります。
Q5. 小規模企業でも必要ですか?
A. 必須です。むしろ小規模ほど損害リスクを吸収できないため、BYOD規程と教育が不可欠です。
まとめ:BYODは「禁止」ではなく「管理」
-
私用端末の利用は現代労務管理において避けられない現実
-
就業規則・BYOD規程の整備、教育、技術的制御の3本柱が必須
-
労務リスク(労働時間管理・未払い残業)と情報セキュリティ対策をセットで実施することが重要
「制度整備と継続教育」なくしてBYODは成り立ちません。“禁止”では守れない。管理と教育こそ最大の防御策
トラブルが起きる前に、社内ルールを整備しましょう。
BYOD規程のほか労務管理のご相談はお気軽にお問合せください
☎:06-6306-4864
《関連記事》
➡従業員10人未満の会社向け就業規則類作成セット(助成金対応済)