NEWS
従業員を辞めさせたい!問題社員・パワハラ上司を解雇する条件と法律リスク【2026年最新版】
2019/09/08
(最終更新日:2025/08/19)
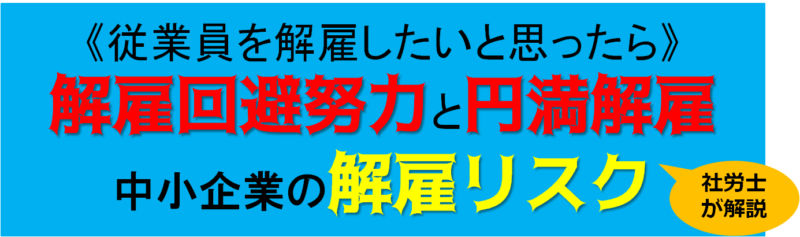
経営者だけでなく部下を持つ上司の立場になると、「もう辞めさせたい!」と思うことは何度もあります。しかし、感情だけで解雇してしまうのは危険です。
法律では解雇に厳しい制限があり、違反すれば不当解雇として高額賠償のリスクも。
本記事では、働かない社員やパワハラ上司を辞めさせたいときに取るべき正しい手順と法的ポイントを解説します。
その解雇、ちょっと待った!!
組織は人の集まりであり、予想外のトラブルが絶えません。近年は特にハラスメント問題や「バイトテロ」、問題社員によるSNS炎上など、人事に関する相談は急増しています。
実際に当事務所に寄せられる相談には、次のようなケースがあります。
✅何度指導しても同じミスを繰り返す新入社員
✅指導に反抗して従わない若手社員
✅SNSで会社批判を発信するベテラン社員
✅堂々とハラスメントを繰り返す部門長
✅経歴を詐称して入社した管理職候補
✅生活のために残業時間を伸ばしている一般社員
こういった社員がいると確かに「辞めさせたい」と思う気持ちも理解できますが、実際には部署異動や教育によって改善するケースも多いのです。
解雇は感情的に決めるのではなく、法律に基づいた冷静な判断が必要です。
☑部署を変えると劇的に働くようになった
☑規則を整備して教育するとよく働くようになった
☑指導方法を変更すると向上心が目に見えて伸びた
☑事情を聴くと別の理由があった
など、簡単な対策で改善することもよくあることです。
感情的になって解雇が頭をよぎることはどの経営者にもあることですが、一度解雇の抱える問題について理解し、対策を冷静に検討してみましょう。
日本の法律上、解雇は高いハードル
日本では労働契約法16条により、解雇は「客観的合理性」と「社会的相当性」がなければ無効となります。
そのため、経営者が「辞めさせたい」と考えても、安易に解雇すれば不当解雇として高額賠償を命じられるリスクがあります。
日本の法律上解雇が簡単に認められることはありません。いわゆる『解雇権乱用の法理』を満たさず解雇を行い紛争に発展した場合、会社がその何倍もの損害を被ることになります。一般的に解雇したい場合であってもまずは退職勧奨(いわゆる肩たたき)を行いますが、退職勧奨は自主的な退職を促すものであり、『退職強要』との境界線は受け取る側によるため、行為に違法性があった場合は解雇同様に不当解雇として訴えられるリスクを抱えます。退職勧奨は大変難しく、解雇関連法律を十分理解しないまま感情的に怒鳴る、大声を出すなどしてしまえば退職強要になるため、例えば話し合いの記録を残すのは当然として、複数で話をするなど対策を講じる必要があります。
退職勧奨は従業員に対する退職金の積み増しや残有給休暇の全消化+αなど、労使間の交渉となるため、相互が合意に至った場合には「退職合意書」の作成と併せて「債権債務不存在確認書」などで後々再燃しないように対策しておく必要があります。
どうしても辞めてほしい従業員が退職勧奨を受け入れない場合は解雇するしかありませんが、もう一度解雇について基本をおさらいしておきます。
《労働契約法16条》
解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする。
解雇の種類と注意点
自己都合退職
従業員本人が辞めたいと申し出るケースです。最もトラブルが少ない退職方法です。
整理解雇(リストラ)
経営悪化などを理由に人員削減を行う場合。
裁判例上、以下の「整理解雇の4要件」を満たす必要があります。
-
人員削減の必要性
-
解雇回避努力(配置転換・希望退職募集など)
-
対象者選定の合理性
-
手続きの妥当性(説明・協議など)
➡ 特に「パワハラ上司」などの問題社員を整理解雇に含める場合も、合理性と記録が重要です。
【参考になる裁判例】 日本食塩製造事件(最判 昭和62年2月16日)
整理解雇の有効性を判断する基準として、現在も参照される代表的な最高裁判例。会社側の人員削減の必要性だけでなく、解雇回避努力の有無が厳しく問われました。
懲戒解雇
もっとも重い処分で、横領・重大なハラスメントなど「就業規則に規定された行為」が必要条件です。
就業規則が整備されていない会社では懲戒解雇はできません。
【参考になる裁判例】 海遊館事件(最判 平成27年2月26日)
セクハラ行為を理由とした懲戒処分が争われたケース。会社側は全員研修など適切な防止措置を行っていたことが評価され、懲戒処分が有効と判断されました。
ハラスメント防止措置を講じていたかが、解雇の有効性を大きく左右する実例です。
普通解雇
能力不足や協調性欠如などを理由とする一般的な解雇。
ただし「改善の機会を与えたか」「記録を残しているか」が判断のカギです。
【参考になる裁判例】 社会福祉法人蓬莱の会事件(大阪高裁 平成30年1月25日)
男性社員が女性上司に暴言を繰り返したことを理由に解雇されたケース。
一審は解雇有効と判断しましたが、控訴審では「解雇は重すぎる」とされ、解雇無効・650万円超の支払いを命じました。問題行動があっても「解雇が最終手段として妥当か」が厳しく判断される典型例です。
(関連ページのご案内)
部下が上司に暴言や暴力を加える「逆パワハラ」でも解雇無効とされた裁判例があります。
詳しくはこちら▶ 逆パワハラとは?裁判例に学ぶ部下対応と解雇の法的ポイント
解雇が認められるケースの例
-
金銭横領など重大な背信行為があり、本人も認めている
-
無断欠勤が長期間に及び、連絡が取れない
-
性的関係の強要など会社の信用を著しく損なう行為
-
試用期間中(14日以内)の解雇や、有期契約の雇止め
解雇が認められないケースの例
-
能力不足や仕事が遅いだけ
-
単発的な遅刻・欠勤
-
正当な内部告発をした
-
プライベート上の不倫や借金問題
-
上司の指導に反抗しただけ
➡ 法律は「改善可能性」を重視するため、指導・教育・配置転換の記録がなければ解雇は無効とされやすいです。
解雇の誤りが招くリスク
-
「明日から来なくていい」と感情的に発言 → 不当解雇認定
-
長時間にわたり退職届を強要 → パワハラ+違法行為
-
解雇予告手当を支払わない → 労基署の調査・是正指導
※近年はスマートフォンでの録音・録画が容易なため、証拠化されSNSで拡散するリスクも大きいです。
まず、解雇に相当する場合の「懲戒解雇」を行う場合は労働基準監督署の認定(解雇予告除外認定)を得た場合のみ即時解雇が認められますが、それ以外の場合には解雇予告手当(平均賃金の30日分)の支払が必要となります。中小企業では解雇予告手当を支払っていない会社が多いのが実情ですが、労働者が労働基準監督署へ申告すると会社に連絡が入り、無視を続けた場合には事実確認の調査(臨検監督)で監督官が来所します。会社の事情が考慮されずに違反切符(是正指導)を切られるばかりか、不当解雇を争われた場合には和解金が数十万円~数百万円に上ることも珍しくありません。
解雇を検討する前に取るべき手順
-
事実確認と証拠収集(指導記録・ヒアリング・メールなど)
-
退職勧奨(合意退職を目指す)
-
配置転換・研修による改善努力
-
外部専門家(弁護士・社労士)への相談
➡ 特に「退職勧奨」は違法な強要にならないよう注意が必要です。合意に至った場合は「退職合意書」や「債権債務不存在確認書」を交わしておきましょう。
まとめ:円満解雇を目指すことが重要
-
日本の解雇は法律的ハードルが高い
-
感情的な解雇は「不当解雇」として大きなリスクを招く
-
教育・配置転換・退職勧奨など「解雇回避努力」が不可欠
-
記録を残し、外部専門家と連携して対応することが安全
「働かない社員」「パワハラ上司」に悩まされても、拙速な解雇は逆効果です。
まずは正しい手順を踏み、どうしても改善が見込めない場合に限って解雇を検討しましょう。
よくあるご質問(経営者・人事向けFAQ)
Q1. 問題社員を解雇する前に必ずやるべきことは?
A. 指導記録の保存、配置転換や研修などの改善努力です。これらを経ずに解雇すると「不当解雇」と判断される可能性が高まります。
Q2. パワハラ上司を解雇するには特別な手続きが必要ですか?
A. 就業規則に基づいた懲戒手続きが必要です。さらに、会社がハラスメント防止研修などの措置を講じていたかも有効性判断に影響します。
Q3. 解雇予告手当を払わないとどうなりますか?
A. 労基署への申告で調査(臨検監督)が入り、是正指導や追徴の可能性があります。無視すると会社の信用を大きく失います。
Q4. 「仕事ができない社員」を解雇できますか?
A. 能力不足だけでは解雇できません。改善の機会を与えたか、他部署での活躍可能性を検討したかが重視されます。
Q5. トラブルを避けて円満に辞めてもらう方法は?
A. 退職勧奨を丁寧に行うことです。退職合意書や債権債務不存在確認書を取り交わし、後日のトラブルを防ぎましょう。
おわりに
経営は常に不安定でなにが起きるかわかりません。サプライチェーンの倒産や自然災害、海外企業の参入による外的要因によってやむを得ず解雇を選択しなければならないケースもあります。しかし、少ない人員枠で最高のパフォーマンスを発揮しなければならない中小企業にとって、問題社員を放置し続けることはできません。
とはいえ、強権的な解雇は他の従業員をも委縮させ、組織のモチベーションを下げることにもなりかねません。どうしても解雇しなければならないときにも、後でトラブルとならないような穏便な退職勧奨など円満解雇を検討するほか、従業員が働かない、働けない理由に耳を傾け、たとえばハラスメント防止研修を受講させたり、長期休暇を取得させたりなど様々な角度からもう一度社員を活躍させる方法について考えることが大切です。
お問い合わせ
従業員の解雇や人事労務管理でお困りの方は、下記フォームよりご相談ください。
外部の専門家を交えることで、トラブルを未然に防ぎ、円満な解決が可能になります。
《関連記事》
➡社員が続かない中小企業の解決策を採用定着専門の社労士がお教えします。
➡職場のパワハラ防止研修に低価格で講師を派遣します【オンライン可】