NEWS
2026年最新版|問題社員対応マニュアル|就業規則・懲戒処分・SNS炎上対策まで解説
2019/10/30
(最終更新日:2025/08/13)

はじめに
中小企業で増えている「社内ルールや常識を守れない問題社員」。
人手不足・採用難の影響で採用基準を下げざるを得ない企業が増える一方、採用後に「こんなはずじゃなかった」と悩むケースが急増しています。
本記事では、就業規則の整備、教育体制、懲戒処分の手順、バイトテロやSNS炎上対策、ハラスメント処分など、企業が取るべき実務対応を2025年最新版として解説します。
2025年最新の労働相談データから見る労務トラブルの現状
厚生労働省が公表した「令和6年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、総合労働相談件数は 120万1,881件 と高水準を維持。
民事紛争相談では「いじめ・嫌がらせ」が最多(54,987件)となり、13年連続でトップとなっています。企業のマネジメント力と法的対応力の両立がますます求められています。
採用した従業員が問題社員で困っています!
人手不足、採用難によってアルバイトや正社員の採用基準を引下げる会社が増えています。数年前までは求人すれば比較的応募のあったエステサロンやヘアスタイルの理美容関係、保育園や介護事業所などのケアサービス業でも、新型コロナ対策や賃上げなど待遇改善への取り組みに遅れた事業所は全く応募が来なくなるなど、特に小規模事業所では深刻な人材不足に陥っているところもあります。
少し前であれば採用しなかったような人材であっても、「応募者が激減して選考どころではない」、「今後応募が来るかわからない」、「誰でもいいから人手が欲しい」といった理由でとりあえず採用してみた結果、問題を起こし後悔している会社も多いはずです。
「モンスター社員」や「モンスター上司」といった刺激的な言葉で話題に上がるこの手の悩みは今に始まったことではありませんが、事業主側としてはせっかく来てくれた従業員に活躍してほしいと願うのは当然のことであり、社内ルールや常識が守れない従業員は何とかしなければなりません。今後もますます深刻化する人手不足と増加する問題社員の対策について、企業側で準備できることはあるでしょうか。
就業規則は小規模企業でも整備するべき理由
労基法89条では、常時10人以上の労働者がいる事業場に就業規則作成義務を課しています。
しかし、10人未満の企業でも規則の未整備はトラブルや裁判となった際に、「ルールが無い=使用者責任」と判断されやすいリスクがあります。また、規則は作成しているけれどもその内容が周知されていないこともあります。そのような事業所が従業員にルールを守れと指導しても、「守るべきルールが無い」と反論されてしまう可能性があります。
遅刻や欠勤を繰り返すアルバイトや、指示に口答えするなど行為自体に問題はあるにしても、従業員に対して基準となるルールを明確にしておかなければ守りたくても守ることができません。「規則が無くてもそんなことは常識」という事業主もいますが、経営の基本から考えれば、規則を作成せずにルール違反を言う事業主のほうが常識が無いと言わざるを得ません。事業主がルールを守らないのなら、従業員もルールを守らないのは常識です。まずは就業規則を整備し周知しましょう。就業規則が厳しいなら、せめて労働条件通知書は作成しましょう。
(対策)
-
就業規則が義務でない企業も労働条件通知書(労基法15条)は必ず作成。
-
規則は整備するだけでなく周知徹底することが重要。
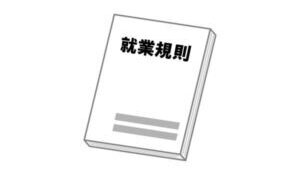
➡10人未満の小規模事業所でも就業規則は必要?【法的義務とメリット】
勤務態度の急変は背景を知るチャンス
全ての従業員には私生活があります。恋人とうまくいかなかったり、家族に問題を抱えているなど、職務に影響のある行動を起こす従業員は何らかの問題を抱えていることが多く、他人に話せない人もいます。誰しも悩みを抱えて生きていますが、急に遅刻や欠勤が増えたり、体調不良が続くなど変わった様子がある場合には注意が必要で、また変わった様子が無いか察知するのも事業主の仕事です。体調面で問題があるようであれば医師へ相談させたり、また長時間労働が続いている場合には当然に心身に不調をきたしますので対策を講じる義務があります。朝からアルコールの匂いを発している従業員の処分に相談を受けたことがありますが、実は連日上司(部長)の宴席に連れ出されており、組織にモラハラの問題があったこともありますので、まずは個人の事情を傾聴できるような管理者の育成や教育が必要です。
〔参考判例〕:社会人経験のない新入社員が研修中に不適切な発言・行動を繰り返したとして解雇された事案について、裁判所は「短期間の研修態度のみをもって解雇するのは不合理であり、他の事情と併せて慎重に検討すべき」として解雇無効と判断しました。(東京地裁令和2年9月28日判決明治機械事件)
▶明治機械事件 東京地裁令和2年9月28日判決(裁判所公式サイト)
(対策)
-
管理職に傾聴スキルを持たせる研修を実施。
-
長時間労働やメンタル不調を早期発見する仕組みを整備。
問題社員への毅然とした対応
就業規則を整備し、日ごろから適切なマネジメントを行っている会社でも問題社員は発生します。
もともとは誠実な従業員が職務や地位に固執して豹変してしまうこともあります。営業で結果を出し続けた従業員が結果の出ない従業員に強く当たるのはよくあることですが、一従業員と上位職者では担う責任が異なります。上司であれば上司としての心構えや組織を最適化するミッション、部下は上司の指揮命令に従い集団に貢献することなど、職務と職責に応じた役割の教育を怠っていないかまずは確認が必要です。対人トラブルを起こす気性の荒い従業員がいる場合は、若い間であれば成長を見守ることもできますが、その個人の資質に問題がある場合には容赦なく処分を下す必要があります。代替要員がいないといった理由でパワハラやセクハラに対して処分を甘くすると他の従業員が離職することになるため、問題行動には毅然とした処分が必要です。優しすぎる経営者がいつまでもパワハラ管理職者に注意できず放置し、部下が一斉退職した例はいたるところであるため、特にハラスメントに対しては心を鬼にしなければ経営は務まりません。経営者は一人に嫌われてでも集団を守らなければなりません。
(対策)
-
職務・職責教育を怠らない。
-
ハラスメント行為は代替要員がいなくても即処分(労働施策総合推進法第30条の2)。
SNS炎上・バイトテロへの防止策
“バイトテロ”と呼ばれる迷惑行為は依然として増加傾向にあり、被害企業には甚大な損害が出るケースもあります。
企業によっては数十億円規模の損害が発生した事例も存在します。
社会人経験の少ない未熟な従業員は行動の先読みができません。情報漏洩やSNSへの投稿が店舗や自身にどのように損害を受けるリスクがあるか、面倒でも教育を行うことが唯一の抑止となります。インターネット上でなくても、若い従業員に飲食店の鍵を渡し閉店後の私的利用によって火災や盗難、その他犯罪行為の現場となる可能性も表に出ていなくても発生しています。従業員の管理者責任を逃れて個人に責任を追及することは難しく、事件が起きた場合には事業主が損害を引き受けするだけになりますので、「ありえない事態は起きる」ことを理解の上予防することが必要です。教育を怠った結果がバイトテロです。なお、雇入時に秘密保持契約や情報漏洩に関する「入社誓約書」を用意し読み合わせと署名させるだけでもかなりリスクを減らすことができます。雇用契約書などと併せて整備を行いましょう。
(対策)
-
雇入時に秘密保持契約・情報漏洩誓約書を必ず交わす。
-
SNSリスク教育を採用時研修に組み込む。
私生活の乱れは処分の対象となるか
社内で不倫していた従業員や宴席での暴力事件、そのほか道路交通法違反によって解雇された従業員は沢山います。中小企業であれば毎日顔を合わせるメンバーが、信じられないような裏があると感情的になるのも理解できますが、業務に影響しない私生活の行動によって従業員を解雇するなど処分を行うことは基本的にできません。本人の自責の念が強ければ解雇されて当然と思いこんでいるケースも多いといえますが、解雇等の重い処分に不満があれば後に処分の無効を争われたり、金銭の要求によって被害の救済を求められることが想定され、訴訟となれば会社は負けるケースがほとんどです。倫理的にどうこうではなく法律上の基準で判断する必要があるため、私生活の乱れを注意する程度であれば当然ですが、減給や降格など待遇を減じる処分を決定する前には、弁護士や社会保険労務士へ妥当性を確認することがリスク回避に必要です。
(対策)
-
倫理的評価ではなく法律上の基準で判断。
-
処分前に必ず弁護士・社労士に相談。
社内教育制度の整備が離職予防になる
近年の採用難によって従来は採用しなかったような採用基準を満たさない層や、新卒や高卒者などの若年層の雇用によって社内の頭数合わせを行っている会社も多くあります。採用基準の引き下げ自体が悪いわけではありませんが、社会人として未熟な若年層や未経験者を採用する場合にはしっかりとした教育を施さなければなかなか一人前にはなりません。にもかかわらず、教育担当者が教育者として訓練されておらず見て学ぶタイプのOJTばかりだったり、新入社員や若手社員向けの研修を実施していなかったりします。それで問題社員呼ばわりされれば若年層らはたまったものではありません。会社としてしっかりと教育する制度を整備することが、幅広い人員を採用するための下地となります。近年はパワハラやセクハラが起きれば大きな問題となるため、上司や教育担当者にも管理職者としての研修を受けさせる必要があります。
(対策)
-
新人研修、OJTマニュアル、管理職研修を体系化。
-
特にパワハラ防止の教育を徹底。
処分の手順は「証拠を残すこと」が鍵
労働基準監督署に懲戒解雇を認められた場合(解雇予告除外認定)のほか、たとえば暴力行為や重大なセクハラなど、就業規則上の重要な処分理由に該当する場合は即時懲戒処分を実施しますが、そうでないモラル違反の場合には、その都度注意するだけでなく、注意の内容について記録したり、経緯報告書を提出させるなどして処分前の準備を整えておくとより効果的です。(本人の謝罪を伴う「始末書」は強制できませんが、「経緯報告書」はなぜそのような行動・行為に至ったのか、本人に弁明させるチャンスも含まれますので、強制できると考えられています。)
「いつかわからないが繰り返し注意した」ではなく、注意した内容、日時、回数などをメモしておくこと。注意程度で治ればそれは素晴らしい前進ですが、繰り返し注意しても治らないのが人間です。しっかり指導の記録は残しておきましょう(労働契約法第16条解雇権濫用法理)。
(ポイント)
-
注意内容・日時・回数を記録。
-
経緯報告書は本人に弁明機会を与えるため合法的に強制可能。
【Q&A:問題社員対応(2025年最新版)】
実際の労務相談で頻繁に寄せられる質問を、法律・判例を踏まえて簡潔にまとめました。現場対応の参考にしてください。
Q1. 就業規則がない状態で問題社員を解雇できますか?
A1. 原則として難しいです。
労働基準法15条の「労働条件明示義務」、労働契約法16条の「解雇権濫用法理」により、解雇には合理的理由と社会通念上の相当性が必要です。
就業規則や労働条件通知書がない場合、「そもそもルールがなかった」として会社側が不利になる可能性が高くなります。まずは規則整備から着手しましょう。
Q2. 私生活でのトラブル(不倫・飲酒事故)も懲戒処分できますか?
A2. 業務に直接的な悪影響があれば可能ですが、そうでなければ原則不可です。
例えば、飲酒運転で免許停止になり業務に支障が出た場合などは懲戒対象となり得ますが、単なる倫理的批判だけでは処分は認められません。判断が微妙なケースでは、処分前に弁護士や社会保険労務士へ相談するのが安全です。
Q3. バイトテロを防ぐため、入社時に何をすべきですか?
A3. 秘密保持契約と情報漏洩誓約書の締結、およびSNSリスク教育が必須です。
「軽い気持ちの動画投稿が数千万円の損害を招く」具体例を提示することで、危機感を持たせられます。採用時研修に必ず組み込みましょう。
Q4. 問題社員への注意は口頭だけでいいですか?
A4. 口頭注意だけでは証拠になりません。
日時・内容・回数を必ず記録し、可能であれば本人に経緯報告書を提出させてください。経緯報告書は本人の弁明機会も兼ねるため、法的にも強制が可能とされています。
Q5. ハラスメント行為をしている管理職に代替要員がいません。処分すべきですか?
A5. 代替要員がいなくても処分は必要です。
ハラスメントを放置すると被害者や周囲の従業員が退職し、結果的に組織全体が崩壊します。労働施策総合推進法30条の2で防止措置が義務化されているため、放置は法令違反となる可能性もあります。
Q6. 試用期間中の新入社員が研修でやる気のない発言をしました。解雇できますか?
A6. 慎重な判断が必要です。
東京地裁令和2年9月28日判決(明治機械事件)では、社会人経験のない新入社員が研修中に不適切な発言を繰り返した事案について、「短期間の研修態度のみを理由とする解雇は不合理」と判断されました。他の事情と併せて総合判断が必要です。
まとめ
・就業規則の整備
・教育体制
・証拠記録
この三本柱が問題社員対策の基本です。
従業員のルール違反や問題社員が多い場合には会社に問題があるケースが多いのもまた事実です。もしも自社で問題社員の行動が目に付いたり、人事で悩むことがあれば自社の規律やルールに矛盾があったり、不整合や不十分な点が必ずありますので一度規則の見直しや教育のための研修が必要です。ルール違反や常識破りの問題社員はいつも多い相談内容の一つですが、まずは自社の労働環境に問題が無いか確認しましょう。従業員を一方的に責めたりしないようご注意ください。上記のようなマネジメント上の問題も全くないということであれば、解雇や退職勧奨も踏まえて検討しましょう。
お問い合わせ
「問題社員対応」「懲戒処分の可否」など人事労務のご相談は、無料相談フォームからお気軽にお問い合わせください。経験豊富な社会保険労務士が実務目線でアドバイスします。
《関連記事》
➡従業員10名未満の小さな会社に就業規則類をセットで作成しています
➡変な人しか応募が来ない。まともな人が応募に来ないと思ったら。
➡従業員を辞めさせたいと思ったら。退職勧奨・円満解雇代行サービス